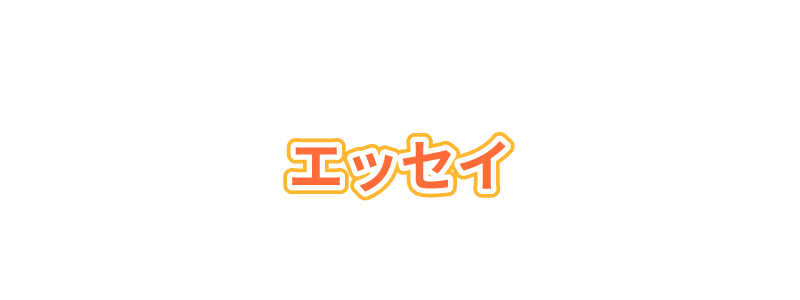2025年04月12日
市立稲毛国際中の受検生を育てるシリーズ
-合格するために学習時間はどの程度必要か?-
受検生を合格へと導くために必要な学習時間数は一体どの程度なのでしょうか?
大手進学塾の中学受験に係る授業時間数は、小学5年と6年の2年間で約700時間~800時間になり、
これに自宅で宿題をする時間が加わりますので、学習時間としては約1,000時間程度にはなると考えられます
(小学5年と6年の2年間)。
一方Brain進学塾では、稲毛国際中に合格するために必要な1対1マンツーマン授業時間数は、小学5年生で入塾した場合、
総計約450時間程度(実績ベース)であり、これが学習時間数の目安となっています。大手進学塾と比べて非常に少ない時間数です。
では具体的に授業時間数を見て行きます。
小学5年生が4月に入塾したケースでは、稲毛国際中の受検までに約20か月、内夏休みの期間は通常期間よりも
通塾の回数が2倍になると考えて、通常期間約24か月と仮定します。24か月ですと、約96週です。
1コマ75分授業を週に2日受けるとすると授業時間数は総計約240時間、1コマ75分授業を週に3日受けると総計約360時間、
1コマ75分授業を週に4日受けるとすると総計480時間となります。
従いまして、週に3~4日の通塾日数が合格のために必要となると考えます。
では、小学6年の4月から通塾を開始した場合には、合格に必要な授業時間数はどの程度になるでしょうか?
総計約300時間程度と考えています。また小学4年の4月から通塾を開始した場合には、総計約570時間程度と考えています。
ここで掲げた授業時間数は、通塾開始時の偏差値が小学4年生及び5年生の場合、約40程度のお子様が対象となっており、
また小学6年生の場合は、偏差値約45~50程度のお子様が対象となっています。
一方通塾開始時の学力の違いによって合格に必要とされる授業時間数は当然変化致します。
Brain進学塾では、お子様の学力に見合った授業時間数を設定致します。
残念ながら大手進学塾では、通塾開示時の学力等お構いなしに決まった授業時間数を強制的に実行させますので、
合理的であるとは言えず、集団授業のデメリットと言えます。
ではなぜBrain進学塾ではこれほど効率よく学習出来るのか、それは1対1マンツーマン指導の為、
受検生一人ひとりその個性に応じて学習内容を変えて授業を行います。
従って学習の無駄がなく、お子様の成長に合わせた学習が出来る事から、学習時間数も少なく出来るということです。
以上
カテゴリ:エッセイ